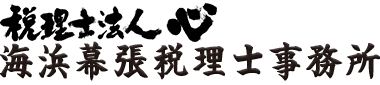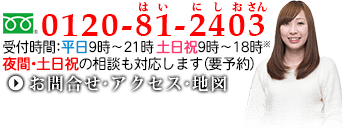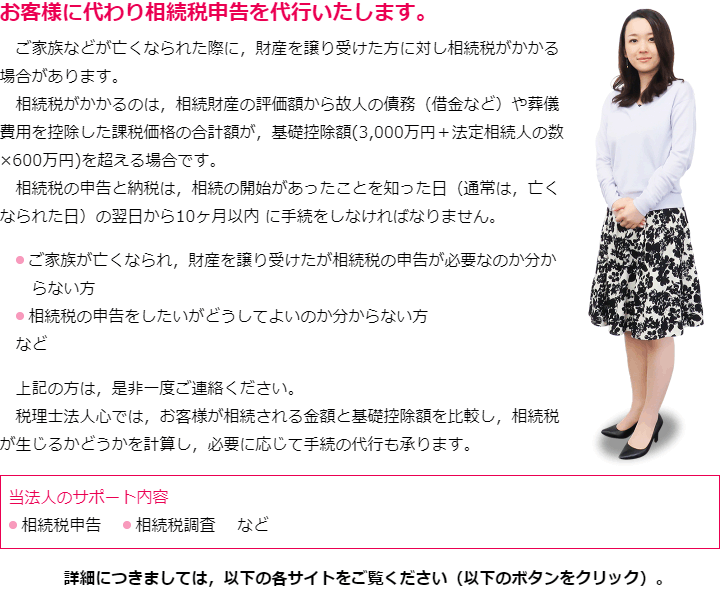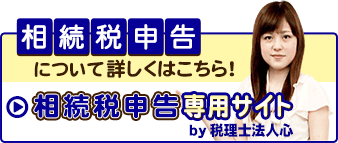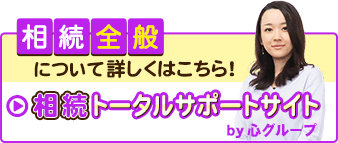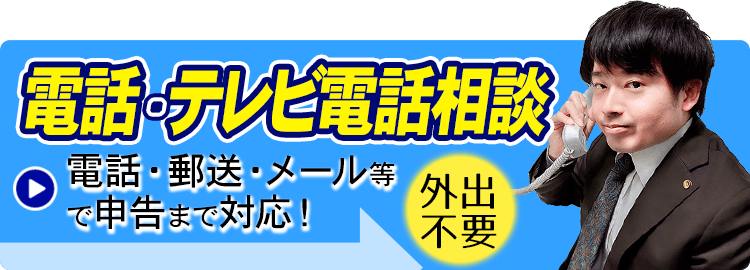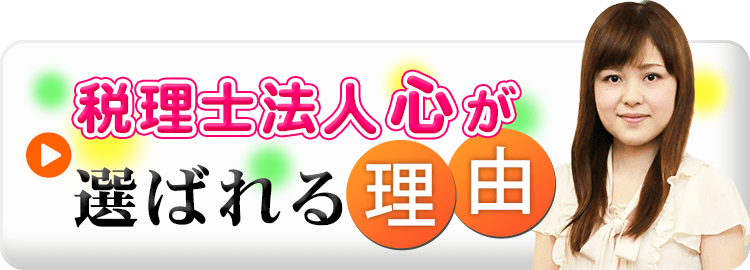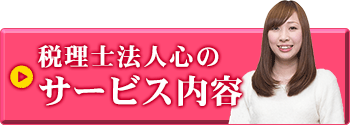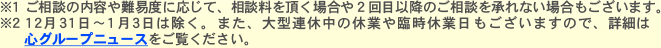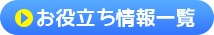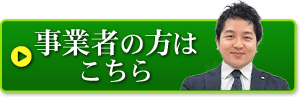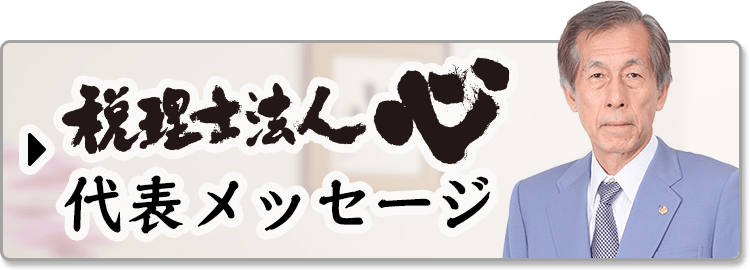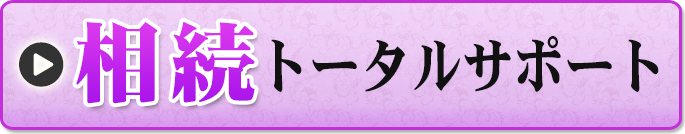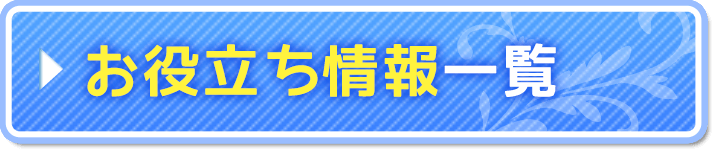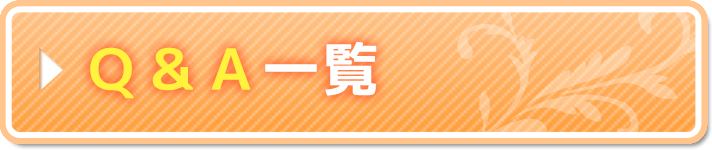相続税申告(相続発生後)
相続税を申告する際の流れ
1 相続税申告の概要について

相続税申告は、一般的には次のような流れで進められます。
①相続人の調査・確定
②被相続人の相続財産・債務の調査
③(遺言がない場合)遺産分割協議
④相続財産の評価
⑤相続税計算・相続税申告書作成
⑥申告・納税
相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
そのため、流れを正確に把握し、期限までに相続税の申告と納付ができるようにしておきましょう。
以下、相続税申告のそれぞれのプロセスについて、詳しく説明します。
2 相続人の調査・確定
相続税の税額は、法定相続人の数に応じて変わってきますので、相続人の調査・確定は必須の作業となります。
相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続税申告の際には、収集した戸籍謄本類をもとに法務局で作成できる法定相続情報一覧図を用いることもできます。
3 被相続人の相続財産・債務等の調査
相続税は、相続財産の評価額に対して課される税金ですので、申告をする前提として相続財産を正確に調査する必要があります。
相続財産調査に漏れがあると、申告漏れが発生してしまいます。
調査の対象となる代表的な相続財産としては、現金や預貯金、自宅などの不動産、株式等の有価証券などがあります。
相続税申告においては、民法上は相続財産とはされない生命保険金等も相続財産とみなされますので、しっかり調査をする必要があります。
併せて、被相続人のローンや未払い金などの相続債務も調査します。
相続債務は、相続財産から控除することができるためです。
4 (遺言がない場合)遺産分割協議
相続人と相続財産調査を終えたら、相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。
相続税を大幅に低減することができる配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、遺産分割協議を済ませておく必要があります。
5 相続財産の評価
相続税を計算するためには、まず相続財産の評価額を算定する必要があります。
現金や預貯金は特に評価する必要はなく、金額がそのまま評価額になります。
一方、不動産や有価証券等は、個別具体的な評価計算が必要になります。
特に土地については相続税特有の評価方法が存在しており、路線価地域の場合には、土地の規模や形状、接道条件等に応じた複雑な評価計算を行う必要があります。
また、建物や土地を貸している場合には、借地権割合、借家権割合を控除します。
6 相続税計算・相続税申告書作成
これまでに調査等を行った相続人の情報、相続財産等の情報をもとに、まず相続税の総額を計算します。
その後、遺産分割協議に基づいて、各相続人の相続財産の取得分に応じた相続税計算を行い、相続税申告書を作成します。
7 申告・納税
相続税申告書が完成したら、税務署に相続税申告書を提出します。
管轄の税務署が遠方の場合には、郵送で相続税申告書を提出することもあります。
申告に併せて、税務署で相続税の納付書を取得し、金融機関等で納税も行います。